 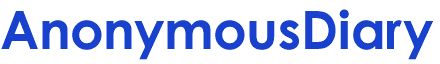 |
はてなキーワード: 院生とは
最初はあんまり仲良くなかった。おんなじコミュでやり取りしてたけど、ある日見たログに「ああいうやつは気を付けたほうがいい、悪いやつかも」って私のこと名指しで書いてあったから
「ログを見た。こんな風に言われる筋合いはない」と文句を言ったら話し合ってくれて、誤解も解けてそこから一気に仲良くなった。
4つ年上の院生で、物知りで頭良くて、たまに通話して音声でやり取りすることもあった。何時間もつなぎっぱなしってこともちょくちょく。
「小説書いてるんだ」っていうので、一度読ませてもらったこともある。私も小説書いてたからお互いに感想言いあったり。
好きな作品の話をしたり。数か月の間だったけど濃密な日々だった。
ネットで出会うとありがちだけど、住んでる場所がとても遠かったんだよね。
私は関西であちらは東北で、でも私は無理してでも会いに行きたいと思っていた。
相手も「いいの?来てもらっちゃうの申し訳ないんだけど」と言っていた。
私は全然問題なかった。私が学校を卒業した後の春休み、会えるのをとてもとても楽しみにしていたから。
でも結局会えなかった。
「やっぱりこういうのダメだと思う、君とは会えないよ」って直前で言い出すの。
あー。真面目だからな。なんだかそういう風に言い出すかもって、予感してたんだよね。
結局そういうところを飛び越えるほど私は好きになってもらえてなかったんだなって思ったけど。
そういう真面目なところ好きだったんだよね。
で、やっぱりそういう風になっちゃったらもう連絡は取れなくなっちゃった。今思えば別にそのまま連絡とって、友達のままで、また機会があったら普通に会ったらよかったのにね。
一度断ったらもう次はないみたいなの、なんだったんだろうなあ。
急に思い出したよ。元気にしてるかな。私はめっちゃ元気だよ。まだいろいろ書いてるよ。
高三や中三の女の子に勉強を教えていると、AVみたいな展開の妄想だって叩かれるかもしれないけど向こうから女を出して誘ってくる事が割とまぁある。
やれ先生のLINEを教えて欲しいと言われたり(規定で個人的なやり取りは禁止されてるから卒業後にしか交換しない)、来週は授業前に少しだけ息抜きに2人でカフェに遊びに行きたいだの、大学1年生の盛った男みたいにアプローチかけてくる(女子は早熟と言われる所以はここにもあるのかもしれない)。
合格したらデートに連れてってなんて言われることはザラだし、過去には体を触って欲しいと言い出す子もいた。
それでも、たとえめちゃくちゃ可愛い子でも、体の発達が良くても、たとえ法改正されて18歳が成人になったとしても、やっぱり彼女らの事は「子供」としか見れない。だから断固として断る。そして担当者を変えてもらって離れる。
子供のうちは大人の男に魅力を感じてしまう時期がある事も知ってるし、何より自分は大人としての責任があるから、彼女らの想いに応えることなんて絶対にできない。
男側からではなく女側からアプローチをかけたのだから純愛なんだと主張している人たちを見ると、それは違うんだと言いたくなって仕方がない。
最近、中東イスラム研究者の池内恵氏が博士号を持っていないことが、X上で話題になっていた。やたらに博士号を持っている側を持ち上げたり、あるいは逆に博士号は重要ではない、実績を見よ、と反論していたりするのが目に付く。
だが、博士号に関しては議論の前提が違う。かつて、そもそも日本の人文系の博士号はレジェンド級に希少であり、真っ当な研究者でも取得できないのが普通だったのだから。90年代以前の人文系の研究者の大部分は、博士課程で博士号を取得することはできないと認識していただろう。
その様相が変わって学位取得が適正化されたのは、池内氏が学部生、院生として過ごした90年代から2000年代にかけてのことだ。池内氏はその変化の恩恵?を授かれなかった狭間の最後の世代なのだと思う。
その点に触れている投稿がなかったので、メモしておこうと思う。
人文系の博士号の取得について認識の齟齬が生じる原因は大きく二つだ。
現在では人文系の博士号の運用は理系の運用に近づいた。だが世代や文理の違いによって事実が見えなくなっている人が多いのだと思う。
90年代中盤当時、大学院について調べていると謎の単語「単位取得退学」に出会った。博士課程に進学し修了したとして、しかし残念ながら学位もらえず、ということはある。ここまでは当然だろう。不思議だったのは、単位取得退学という言葉がまるで学位のような扱いだったことだ。プロフィール欄に堂々と書くようなものか?と思った。
調べるとどうやら人文系で博士号を取得するのは非常にマレだということだった。それゆえに単位取得退学が学位のように通用していたということである。
ざっくりと状況を把握するには、下の 3.4.2日本の博士号取得者 (1)日本の分野別博士号取得者 あたりを見てほしい。
[科学技術指標2021・html版 | 科学技術・学術政策研究所 ](https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2021/RM311_34.html)
実態としての運用はどうだったか。その雰囲気はこの辺のWikipediaの記事に詳しい。
[単位取得満期退学](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E4%BD%8D%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%BA%80%E6%9C%9F%E9%80%80%E5%AD%A6#%E4%BA%BA%E6%96%87%E3%83%BB%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%B3%BB%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%89%B2)
「1989年以前の東京大学大学院人文科学研究科では、大学院生にとって課程博士論文は書かないことが原則で書くことは例外であったという」
少なくとも90年代以前では、人文系の研究者がキャリアの初期に博士号は困難であったというより、ほぼ不可能だったみて構わない。かつて人文系の博士号はキャリアの晩年に差し掛かってそれまでの功績を評価してもらうもの。今のように博士課程を修了した時点でキャリアの出発点となるような資格のようなものではなかったのだ。
この状況は1990年代に入ると徐々に変化する。
[23.博士学位授与数の推移と授与率:文部科学省](https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1407428.htm)によると、博士授与率は、
平成3年度(1991年度)に人文系4.7%、工学系78.1%だったものが、平成13年度(2001)年度では、人文系で23%、工学系では88.6%と変化する。まだ差はあるものの確実に変化している。
いずれにせよ、2000年前後は、「博士課程を修了して真っ当な評価を得れば博士号を取得できる」という普通の状況に至るまでの長い変化の途中の時期だった。
博士号を取得する人の数は増え続けている。ただご存知の通り、その活躍先が十分あるとは言えない状況だ。
このことで企業側の受け入れ姿勢を批判する向きもあると思うが、それは間違っていると思う。かつての日本の博士号(人文系)の授与が異常だったのであり、企業はそれに適応しただけだろう。変な運用を続けていた大学に責任がある。企業の変化にはまだ時間がかかるだろう。
現在、特に人文系に関して博士号は多く取得されるようになったが、だからと言って価値が軽くなったという話ではない。
ただ時代が違ってしまうと、まるで別のものになっていることは押さえておきたい。別の分野の研究ともなると尚更比較するのは困難だ。
私自身は結局アカデミアとは無縁のキャリアになったので、個別の研究室の中のことを知る由もないが、おそらく池内氏が博士課程に在籍していた2000年前後は博士号の扱いの転換期だったはずだ。その当時は学位を取得することは不可能ではなかったが当然でもなかった時代だと言える。
まして、仄聞するに、池内氏は学会の因習、悪弊に対して相当の武闘派であったようだから、そう簡単に学位を取得できる状況だったとは思えない(これは憶測だが)。
池内氏の中東、イスラムの分野の研究における業績は既に輝かしいし、一般向けの著書や寄稿も数多い。加えて組織の設立・運営、後進の育成など、並みの胆力ではこれだけのことはできない。
現在、この世界情勢のもとで池内氏の解説や発言は、信頼のおける言説としてますます重要になっていると思う。
当人にとっては博士号の話など大きなお世話で、拘泥もしていないと思う。
ただ、一般の人が博士の扱いの変遷について知らず、この話題によって氏への信頼に一点でも曇りを生じそうな人がいるなら、それは違うとは伝えておきたい。
目的はかつて大学生だったときみたいなモラトリアムを楽しむことだ。勉強する気はゼロ。
夜遅くまで雑誌や新聞や適当に目に付いた本を読みながら図書館居座ったり、学食でぼーっとしたり、生協に冷やかしに行って学割で本買ったり、雀荘で頭痛くなるまで麻雀打ったり、キャンパス周辺の飲食店制覇したりしたあの楽しい生活に戻りたい。
無職は世間体が悪いので嫌だし、もう学部は卒業しちゃったので、どうせなら大学院に潜り込んで意識低い学生生活をもう一回やろうと思ってるんだけど、
「単位なんて取る気ないし論文も書く気ないです」って姿勢でも周りから文句言われず快適な院生ライフを送ることは可能だろうか?
院がいいんだよなあ。
どうしたらいいのだろう。本当にわからない。
Google先生も知らないらしい。というより、モンスター社員を相手にする側の事しか教えてくれない。
大学生活後、新卒入社。最初こそガムシャラに働いて評価も上々だったはずだが、すぐに精神的に患って心療内科の通院生活。その時に発達障害の傾向があることは認知した。以降は最初ほどの熱意はないにしろ、求められている業務をこなし続けていたつもりであった。今思えば、いつまで経っても電話応対が下手くそなままだったが。
患ってすぐの頃に配属や業務内容は調整していただき、最初は簡単なタスクや期限が厳しくないタスクを割り振っていただいた。当時の会社や上司・先輩にはかなり配慮していただけたので、環境としてはとても恵まれたものと言える。心身の不調で休みがちな状態は続いたが、それでも小さな成功体験を積み上げて人並みの自信を取り戻すことはできた。おかげで個人的に楽な道ではなかったが、それでも新卒入社から現在のアラサーになるまで、自分なりに頑張り続けることはできた。
仕事に慣れてきて、普通のタスクも任せてもらえるようになった。それも問題はなかった。問題は、最初の計画になかった中期的なタスクが上乗せで積み上がった時だった。タスクの総量としてはそれでも、業務時間中の余裕が減っただけで、週40時間の範疇で捌けたかもしれない。ただ、後から追加されたタスクが計画に無かったものなので自分のペースが崩されたこと、そして、若干理不尽な経緯で増えたタスクだったこと。それ故なだけで、精神的に参ってしまったのである。先輩だと最初だけ愚痴って捌いたのかもしれないが、それが自分にはできなかったのである。
今思えば、この段階でタスクの拒否なり相談なりすればよかったのだが、それを自分1人で抱えてしまった。パフォーマンスが落ちている状態なので、タスクの処理は間に合わない。そしてそれを説明する能力もなく、「事前に報連相もないままタスクが遅れている」ものとして処理されていった。結果、余計に病んで休みがちになり、タスクがさらに遅れる悪循環に陥った。無理に時間外で取り戻そうとして、大して戻らない挙句に身体を壊すこともやってしまった。
社会人として仕事をしていれば、仕事仲間に悪意がない環境に恵まれてもなお多少のストレスは避けられないものだとは思う。そして繰り返すが、一応は週40時間でなんとか収まるようなタスク量だったのである。最悪40時間を溢れるとしたら、誰かに相談はできたはずである。だが何もできなかった。社会人1年目のエピソードとしてならばまだ良くある話なのかもしれないが、新卒採用から働き続けてアラサーとか中堅とか言われるようになってもなお、これなのである。成長していたつもりで大して変われてなかった自分に、久々に嫌気がさした。
通常の業務で起こり得るような、軽微なストレスにも耐えきれず精神的に参ってしまう。そして絶望的にコミュニケーションが苦手で報連相ができず、勝手に1人で抱えて手遅れになってしまう。これが、自分がモンスター社員かもしれないと思った要因である。世の中には色々な系統・程度の問題社員がいると思われるが、自分のこれも大概厄介なのではないかと思ってしまった。
ただこれを認知できたところで、自分にはどうしていいのか本当にわからない。人事や上司に「自分は問題社員ですか」と聞くのが正解なのだろうか。聞くにしても、上手く経緯を口で説明できる自信はない。転職するにしても原因がこれなので、同じことの繰り返しになってしまうだろうと思ってしまう。というより、最初に配慮してもらったように、会社自体はホワイトな方なので、下手に転職したら悪化する気がするのだ。
世の中は多様性がどうとか謳っているが、社会に適応しきれずに悩んでいる人がここに1人いるのだ。果たして、どうすればこの人は幸せに生きていけるのだろうか。本当にわからない。
自分も匿名じゃないブログを書く身で、その日も何気なくはてなブログランキングを見ていた。そこで気になった匿名ダイアリーが、事の発端である。詳しくは当該記事を見ていただきたいが、モンスター社員に振り回される人たちの話だ。SNSでも話題になってたのかもしれない。
今週のはてなブログランキング〔2023年9月第1週〕 - 週刊はてなブログ
自分としては記事本体や記事への反応、その後のGoogle検索で初めて「モンスター社員」という言葉を知ることになった。そして悲しいことに、自分のことで心当たりのあるような記述が何度も出てきてしまったのだ。幸か不幸か頭は回る方なので、単なるバーナム効果ではないとも、なんとなく理解してしまった。モンスター社員の特徴自体もこたえるものがあるが、それ以上に周りの社員や人事の苦労話を見るのが辛かった。泣いちゃった。
それでも、迷惑をかけてる現状を打破したかった。少なくとも、自分がそういう社員だと気づけたことは大きな一歩なのだろうと信じている。そう思い込みたいだけかもしれないが。
しかし残念ながら、こんな相談をできる相手が身の回りにはいなかった。人事としても、特段親しいわけでもない社員からこんな話をされても反応に困るだろうし、逆に退社の相談だと受け止められたらこちらが困る。人付き合いが苦手で親しい人は社内におらず、相談できる親しい人は別要因で退職してしまっていた。プライベートの友人もそこまで真剣に考えてくれるとは思い難い。心療内科等のカウンセリングなら気持ちが楽にはなるだろうが、今回ばかりは楽になるだけでは足りない。
1週間ほど悩んだ挙句、このままでは結局何も進まないので、ひとまず言語化した次第である。社会に適応した人たちからはどうしようもない人間に見えるかもしれないし、共感できる人がどれだけいるかはわからないが、こういう人間が自身でも悩んでいるというのを知っていただけるだけでも御の字である。
今年の4月。
念願叶って非正規から正規職に転職した某私立院卒の26歳、社会人3年目。
だが、転職して4ヶ月が経った今、仕事を通して生きる目標を見失った。ここ数日、平日の朝を迎える度に「自分はなぜ、この仕事に就いたんだろう」と自問自答を繰り返し、「仕事に行きたくない」という思いばかりが頭に浮かぶ。
別に仕事が激務な訳ではない。残業なんて今のところ忙しかった時期でも月20時間程度、現在はほぼノー残業で、定時上りもザラな職場だ。
では、人間関係やパワハラ上司に嫌気がさしたのか?というと、そういう訳でもない。確かに直上の上司は少し厳しいところはあるものの、決してパワハラをするようなタチの人間ではない。むしろ僕の目線では、それなりに自分の事を思って仕事を指導してくれる良い上司だと思っている。職場の人間関係も若返りを図っているためか、自分を含め20代の若い人が多いので、比較的良好だと感じる。
傍から見る分には「なんてホワイトな職場なんだ!」と思うだろう。実際、僕も今の職場はホワイトだと思っている。
だが、それでも生きる目標を失うに足るほどの辛いことがある。それは、「仕事に対する重責に自分自身が耐えられない」ということだ。
あまり具体的には書けないが、現在、僕がいる部署は(その手の業界では)日本でもそこそこの知名度を誇る。
業界人に「今、◯◯◯で働いています」と言うと、「えー!◯◯◯で働いているんですか!?凄いですね!」とそれなりのレスポンスが返ってくるレベルの部署だ。
だからこそ、特に幹部クラスの上の世代には「ここで働いている自覚とプライドを持ちなさい」という意識が強い。
それがハッキリした形で僕に返ってきたのは、転職して2ヶ月後の忙しくなりつつあった頃。
その時、僕ともう一人の若手(1年上の先輩だが、年は僕より下)が仕事を進める上で失敗し、そのザマを見ていたトップが、
「あの子たち、仕事が出来ないね」と、こぼしたのを直上の上司が聞いたらしく、鬼の形相で事務所に飛んできて、二人共々こっ酷く怒鳴られた。その後、さらに上の上司から「アンタらは◯◯◯の担当なんだから、その事にもっと自覚と責任を持って仕事に取り組んでください(要約)」というお気持ちメールが届いた。
この時は、自分の不甲斐なさに反省しつつ、「もっと頑張らないとな…」と思った。
だが、徐々に仕事に慣れつつある中で、仕事でのミスは一向減る気配は無かった。先輩から頼まれていた仕事は忘れる始末で、これを書いている今日とかも、上司から「仕事の段取りをもっとちゃんとしなさい」と怒られた。僕自身、注意される度に「次は気を付けよう」、「忘れないようにしよう」と思うのだが、どこからか気持ちが抜けるのか、中々思うようにいかず、その度にいくら気を付けても改善できない自分が嫌になり、自己嫌悪に陥る。
「オイオイ、まだ入りたてなんだから、そのくらいのミスは誰でもあるさ」、「若いうちはミスして当然」というのは簡単だ。だか、一応2年間の社会人期間もあり、院卒としてのプライドがあるので、そうした割り切った気持ちよりも先に「なんでうまく仕事が出来ない、回せないんだろう」というモヤモヤする気持ちの方が強く出ててくる。そして、段々「この仕事、やっぱり合って無いんかな」と思えてきて、
遂に「面接の時に『◯◯◯をしたいんです!』と言い切ったあの時の思いは、受かりたいが為の啖呵だったんだな」と気付いて、仕事での目標を見失った。
だが、こうして目標を失った今に思い返せば、そもそもの話、「この仕事が好きじゃない」ってところに行きつくのかもしれないと思っている。
少しばかり話はズレるが、今の仕事は学生時代からやって来たことをそのまま"プロ"として仕事にした感じである。だから、両親や周りの人からは「好きなことで仕事しているんだから、羨ましいことだよ」と度々言われる。じゃあ学生時代どうだったかたいうと、あまりいい思い出が多いとは言えないなぁと思う。勿論、それで院まで行って論文を書いたのだから、それなりの偽らざる感情は持ち合わせていたとは思う。だが、思い返せば辛いことの方が多いなと。
院試を受ける前はあまりにもの出来なさに焦り、やる気のある真面目なゼミの同期とも対立して人間関係が拗れたこともあって、「本当にこの道でいいんだろうか」と思い悩んで、精神的に追い詰められてカウンセリングを受けた。院進後には、自分の院生としての自覚の足りなさから、やる気のある学部生の後輩から突き上げられ、指導教官の部屋で後輩同席のもと教官から説教喰らったこともあった(特に説教された件はかなりのトラウマになってる)。
結局、こうした過去を今も引きずったままだから、仕事にしている今が1番辛く感じるのかもしれない。
そして話は元に戻るが、こうやって目標を失った今、どうしたらいいんだろうかと思う。
業種を変えようにも、異業種のスキルも経験も全く持ち合わせてない。何か新しく身に着けようと思うが、なかなか体も心も動かない。では今の仕事を耐えて続けるのが最善かと言われたら、それはそれでプレッシャーに耐えきれなくて発狂する未来が容易に想像できるし、自分の本心を偽ってでもしがみ付くのも違うかなと思う。
本当にどうしたらいいんだろうか。
でも面白いと言ってる意見は結構見るしPV数も多いっぽいんだよね。
ゆーてジャンプ+の日曜日ってニッチ向きかつ変な尖り方した作品ばっかでPV元々ばらけてっからここで1位取ったからって参考になるかと言われると微妙なんだけどさ。
でもコメントとか見る限りは普通に楽しんでる人はいるっぽいんだよね。
自分はコロナ設定・院生設定・偉人設定・霊界設定・恋人設定・メンタリスト設定なにもかもが全く生かされてないチグハグな漫画だなとしか感じられてないんだけど、これ楽しめたという人はどこが楽しかったんだろ?
1話では歴史上の人物が現代に出てきてその暮らしにビックリしてる様子とかないから「Fateみたいに現代知識事前インストールなのかな?いや……そもそも亡霊ってことは現世に1000年留まっているんだから一連の進歩を追っているはず……自分たちの過去を知らないのは見たくないものは見ないように暮らしてきたのか?」と考察してたのが全部ひっくり返ってずっこけたのが面白かったとかそんなノリ?
高度過ぎるぜ。
わざわざ歴史上の人物を読んできて承認欲求モンスターにして終わりみたいなノリが面白いのかな。
いやでもFGOとかも確かにそういう系統だし今どきの流行りなのか?
恋姫†夢想みたいな感じで偉人を冒涜してハワワご主人さまとか言ってるのが面白い的な?
多分違うんだよこういう風に考えてる人が「面白い」と言ってるんじゃなくて、もっと頭の上っ面だけ見て何となく面白ーいと言ってる感じなんだよね。
でもそのノリが分からん。
わざわざ歴史上の人物の亡霊を呼んでおいてなんでこんなことしてるんだろうって疑問が強烈過ぎる。
どうやったら楽しめるんだろう。
謎すぎる。
教えて欲しい。
後学のために。
それな〜〜僕はバリバリ人文系の修士からマスコミに就職した者なんだけど
研究の内容とはあんま関係ないことやってるよ。新聞の記事書いてる
記事も、読みやすさのために取捨選択をしたり、方向性を決めたりするし、”ニュースバリュー”が重要だから
例えば、ある事柄にA・Bそれぞれの可能性があって、仮にBが致死的なものであれば、それを大きく取り上げざるを得ない
そういうのを「知的誠実さを欠くのではないか」と、最初は迷ったりもしたな
でもまあ、そういうのが作法なんだなと理解したから気にならないよ
そろそろ大学の連中も、好き勝手やって国が金出してくれるのが社会的に正しいみたいな意味のない甘えは捨てた方がいいよな
そういうこと言ってる教員や院生を見ると鳥肌が立つようになった
前なんか東洋大学とかのやつが「日本は院生に厳しい(給料が出ない、就職がない)」とか言ってて笑っちゃったけどさ
そもそも、彼らの主張の本質は「こんなに良い大学を出たのに/高等教育を受けたのに、給料が安いのはおかしい」というものだから
文化を尊重しない国は衰退する(キリッ)とか言っちゃって、でも君ら社会のために何かしようとかないでしょ?
どんな小さな研究も学問的蓄積に貢献していると言えるかもしれない(裾野を広げるという意味でも)。でも、なぜ社会が君の面倒を見て当たり前だと思うのか
なぜ、今や全入状態の大学院なんかに入って手遊びやっただけで、労働者階級から吸い上げた資本で(何より「君が」!)高等遊民でいられるべきだと思うのか
当方、大学院でメディアの影響を社会学的枠組みを用い統計学的手法で研究していた。師事していたのはその道の大家。(※大学名とか教官名は特定防止のため伏す)
まあ出来は壊滅的に悪かったんだけどね…
まず言っておくと、強力効果論のようなある特定のメディアの影響モデル「だけ」をつかってメディアの影響をすべて測ることは不可能。
もちろん今も研究は多々行われているけど、メディア環境自体激変を続けていることなどから今後も影響評価に対する統一的知見が出る確率はほぼない。
仮にそういう理論を完成させたら即東大情報学環あたりのポストはゲットできるはず。
実際の研究においては調査の都合上ある特定の議論に沿って分析を進めていかざるを得ない。
仮に複数の議論を包括したうえで研究を行う場合、特に実際にデータを収集して行う調査においては研究に沿った形で逐一面接項目や質問項目を作らなければいけない。
そうなれば項目も膨大になってデータ収集される側の負担も大きく増す。負担が大きい調査を薄謝で行ってくれるような優しい人間はそんなにはいない。
結果統計学的に意味のあるデータが集まらず、満足いく分析ができない可能性も大きい。
メタ分析に関してならできなくもないといいたいけど、その対象は調査データだったりするので調査の段階で軒並み躓くとメタ分析の意味も薄らぐ。
あと、メディアの影響に関してはその人が置かれている環境や属性によっても大きく異なってくる。
その場合、異なる環境の人同士を十把一絡げにまとめて単一の尺度で分析することが妥当なのか?という問いもでる
(※先述の通り実際の研究では「大人の事情」でそうせざるをえないことが多いが…)
>「水からの伝言」と違うの?
まず条件を統制して研究することが可能な自然科学と、それがほぼ不可能な人文科学の研究は本質的に異なる。
当然理論の再現可能性に関しても限定的になることは留意しなければいけない。
ただ、それを理由に「理論に妥当性がない」と言いだしたら人文学の見地はすべて棄却せねばならないことになる。
元のエントリ、一見専門用語をちりばめるなどして「それっぽく」見せているけどよく読むとツッコミどころしかないの。多分ネットの耳学問だけで情報を知った半可通だからかな?とは思う。
もちろん俺もどうしようもなく不出来な院生だったし人のこと偉そうにいえんがな。実際こんなサビたなまくら未満の論駁しかできないわけだし。
自分も浅学非才だし、もっと本とか論文を読んで知識をつけなきゃなとは常に思っている。
20年くらい前は大学の研究者の人達とか大学院生とか、実験の気分転換と称して、スラドとかいろんなところに書き込みしてたじゃん。
「初めて米国学会で発表するので超緊張してる。寝不足と時差ボケで口の中カラッカラ」みたいな書き込みとか「院生だけど5時間睡眠ですが何か?」みたいな若々しい書き込み横目でみながら「あーわかるわかるー」「みんながんばろう!」とか思ったもんだよ。
15年くらい前は、「いまベンチャーに入社してシリコンバレーに来たところ、これから投資家向け技術説明会だ、頑張るぞ」みたいなブログとか結構あったような気がする。(気がするだけだけど)なんかこの数年くらいで一気に学問系、(技術力のある)スタートアップ系の人影が「その辺」から消えてみえなくなって
代わりにいわゆる常駐系の人達の背景知識見識のないクソコメントで埋まるようになってきた。ここ1,2年は素人さんのおもいつきデマつぶやきがまとめられてブクマされて(これはひどいという晒し上げなんだろうけれど)流れてくることが増えた。
チャットGPT関連のネタは流石にまあ専門性あるかな、って位だけどこれもトレンドモノで
きちんとバックグラウンド抑えた基本的な話があんまりなくて、AIで萌え絵やポルノかいた!やったー!(それはそれでいいけれど)みたいな話であふれている。世の中カテには毎日女性が痴漢された盗撮されたレイプされた胸を揉まれたみたいなエントリが並んでいて啓蒙活動員の皆様の活動にうんざりする。結論としては日経電子版とかフェイスブックとかに戻るしかないのかな、って感じです。
文系大学院のDなんだけど、今年入ってきたM1の後輩に思うところがあるから愚痴らせてほしい。
その後輩はなんて言うか、無菌室で培養されたって感じの純朴なヤツで、すげー勉強するし学問に対するやる気もバイタリティもある。ちなみに男。
そいつの研究に対する熱意や努力は普通にすげぇなって思ってるし、俺も見習わなきゃなって自分の怠け具合に危機感を持つくらいなんだけど、そいつ、どうも協調性がないんだよね。
まず4月に一度面倒事を起こしてる。
俺らの大学院は合同研究室制になってて、専攻全体でひとつの研究室。で、教授ごとにゼミがある。分かりにくいだろうけど、詳しく書くと身バレするからこれくらいで。
研究室のグループLINEを作ってるんだが、新M1の中でその後輩(仮にAとする)だけLINEをやってなかった。
今の子はLINEやらない子が多いって聞くし、時代だなーって思った。
で、専攻内の連絡事項とか大事なやり取りは全部LINEでやるから、「申し訳ないけどLINEを入れてほしい」って頼んだんだ。
そしたら頑なに「入れたくない」って拒否してて。理由を聞いても「LINEはやりたくない」の一点張り。
LINEをやってない子が他にも何人かいるなら、時代に合わせて連絡網を別の形に変えようとは思ったけど、そいつ一人だけだから、Dの俺ら(取りまとめ役)もどうしたもんかと思って。
じゃあメーリングリストにするか?って話も出たけど、「研究室開室しました」とかの細かい連絡をいちいちメールで流すのも…となった。
じゃあdiscordとかSlackは?って意見が出て、アカウント持ってない人は作らないといけないけど、それなら大丈夫だろうってAに話した。
でもAはそういうメッセージアプリを絶対に入れたくないらしくて、その案も拒否された。
俺はその時点でワガママがすぎるって思ったけど、入ったばかりのM1に小言なんて言いたくないし黙ってた。
結局周りが説得して、AはLINEを入れてくれたんだけど。
次にモヤッたのが、ゼミ費の扱い。
毎年大学から各ゼミに補助費が出て、そのお金は教授とゼミ生が使い方を決める。
例年うちのゼミでは飲み会に使ってて、この3年はコロナがあったから、補助費で教授が図書カードを買ってゼミ生に配布してた。
今年はどうする?飲み会復活させる?ってなって、他のみんなは補助費で飲み会やりたいって言ったけど、Aだけは図書カードがいいって即答。
ちなみにゼミ費で飲み会をやること自体は大学側からも許されてる。
そういう機会でもないと、教授とじっくり親睦を深められないからかな。懇親会的な扱い。
この2つの出来事があったから、俺の中でAは「純朴すぎて協調性がないやつ」ってイメージがついた。
けど俺がアラサーだから、価値観が古いだけなのかなとも思ってた。
その後もAは専攻全体の飲み会とか、M同士の飲み会とか、全部欠席してる。
酒を飲むの自体は好きって言ってたから、飲み会って場が嫌いなのかもしれない。
まだコロナも蔓延してるし、感染が怖くて出てないなら分かるけど。
俺が古い価値観の人間&コロナに対してもう楽観的になってるから、Aに対して穿った見方をしてしまうのかな。
ただなんかモヤモヤするのは、このままだと専攻内で孤立するかもしれないことに、A自身が気づいてなさそうだから。
研究って一人でやるもんだけど、一人じゃ出来ないものでもある。
同期や先輩や教授と日頃からコミュニケーションを取っていないと、ちょっと躓いた時に気軽に相談しにくいし。関係性が出来てないと気軽に質問しにくいって、院生なら分かってもらえると思う。
院生同士のちょっとした雑談とかから知識を得られることもある。
別にそれは飲み会じゃなくても、日頃から研究室で周りとコミュニケーションを取っていたらできることなんだけど、どうもAは研究室内でも周りと雑談とかあんまりしてないんだよな。
他のM1は最初の新歓とかでコミュニケーション取ってるから、相手の人となりとか分かってて接してる雰囲気あるんだけど。
Aに対しては、なんとなく距離がある感じ。
最初に書いたように、Aはすげー勉強するし、研究発表でも人の2倍のボリュームをやってくるんだよ。
ただ中身はまだまだだから、これから壁にぶち当たるだろうなってのが見えてるんだけど。
そうなったときに、誰にも相談できなくて孤独に陥りそうな気配がしてて怖いんだ。
もちろん俺らも先輩として面倒みるつもりだけど、研究の悩みや孤独って、むこうからヘルプ出してくれないと、こっちからは手を差し伸べられないんだよ。どう差し伸べたらいいか分からないし。
俺が考え方古くて要らないお節介を感じてるだけで、何も考えないほうがいいんだろうけど。
なんかモヤモヤするんだよな。
研究室のグループLINEを作ってるんだが、新M1の中でその後輩(仮にAとする)だけLINEをやってなかった。
(中略)
じゃあメーリングリストにするか?って話も出たけど、「研究室開室しました」とかの細かい連絡をいちいちメールで流すのも…となった。
狭い世界なので適当にやってしまうのは自分も所属しているのでわかりますが、いろいろな人がいるのだから筋は通すべきだと思います。
メーリングリストがメインで、それとLINEをapi連携、大学院生なら30分もあればゼロからでもできるでしょ。
次にモヤッたのが、ゼミ費の扱い。
これはおそらく勘違いで、補助費は「学生会」から出ているのではないでしょうか。
その場合、使途の範囲は、大学でも教員でもなく学生(学生会)が決めているはず。
そして、補助費は「全員に均等に配るべきもの」ではないはず。(それなら最初から徴収する学生会費を減らせ、という話になる。)
「懇親は全体に有益なので、それを促進するために補助をする。ただし、参加者数に応じて一人あたりいくら。」みたいなのが根本的な原則のはずで、それを雑に理解して運用しようとするので、想定外の状況でごたごたする。
もし上述のようなルールなら、A氏の意見(図書カード)は否決して良い。
もし配慮するなら、「懇親会の欠席者には図書カードを支給する」で良い。
言っちゃ難だけど、大学院でDまで来ておいて、考えが雑で筋が通っていない。
そんなことで、複雑な社会やら文化やらにアカデミックにアプローチできてるの?