 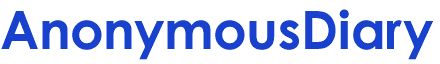 |
はてなキーワード: 実定法とは
あのさあ、分からないならもうしゃしゃり出てくんなや大嶋。相殺の制度は民法511条に規定している。債権債務の円滑な処理が目的であると最高裁が示しているが、法律の規定の目的が
あるのかというと、実定法学上、教えてられていないものである。判例で
文言とその本質に鑑みれば、と書いているのは、たいていの最高裁の法解釈は、 文言と本質の調整を行うので、このように書いていてそれをする場合に、民訴法598条なども
絡んでいるので、 doing systematically categorically なのである。 立法者は神と考えられているので、 立法者が何を考えていたかが問題になることがある。
お前が言っている秩序とか道徳とか個人の尊厳というのは大域(憲法)の方の話で、お前の話には1つも技術的ないし、定理的なかっこいい内容がない。
警務課の後ろに座っていて笑っている司法警察員のおっさんもさあ、偉そうなだけで、テクニックの話がないんだよ。だからお前のどこに魅力があるんだよ。
この問題で張り切っているひとに慶応大学大屋教授がいる。この方は法哲学の先生と思っていたのだが実定法の人だったのだろうか?
それにしてもこのひとの投稿を読んでいると、横領のことなどはちょっと的外れな気がする。
フォロワーがいることは”地位”なのか。例えばフォロワーがいないひとがいったとしてもそれは天に向かっての独り言、4万人のフォロワーがいれば、4万人に向かってしゃべることになる、ということを考えろということですね。
しかし実際はこの方が横領について”地位”と書いているが、それはそのとりで、一般社員が横領できる金額と役員、取締役などに上がっていくに従い、横領できる”額”は増える。
それとSNSは同じなのか、違うのか。
最近の処理水放出に関して色々な意見が出ている。問題なしとする意見も多いが、そうでない意見も多く割れていると言っても過言ではない。
twitterでも、有象無象の匿名人間だけでなく高名な学者でも政府見解を批判し処理水放出に反対する意見がある。例えば
宮台真司 https://twitter.com/miyadai/status/1697486382837407787
水俣で言ってごらん。湾とは違うってか。だったら地球規模の海流シミュレーションと魚介分布の動的重ね合わせを精査しな。精査する義務は放出側。実定法は「推定無罪の原則=疑わしきは罰せず」。環境汚染は「予防原則=疑わしきは回避」。何も知らないお前がゴミ。
山口二郎 https://twitter.com/260yamaguchi/status/1698544796313497990
そもそも廃炉を前提とした処理水放出というやり方が、世界を欺くということを言いたかったわけです。マイナンバーカードと同じく、何段階か遡って、政策の意味を考え直すという態度が日本の政府、官僚にあればとつくづく思う。
牧野淳一郎 https://twitter.com/jun_makino/status/1697964368850571399
第三は、内部被曝の評価が生物濃縮や、半減期を考慮していないこと。告示濃度に対する比率がかなり大きい I-129 は海藻によって数千から数万倍濃縮される上に、半減期が 1570万年と長い。
いずれも一流大学に属する高名な学者であり、様々な論点を述べている。
学術会議もさ、「日本学術会議とは」(https://www.scj.go.jp/ja/scj/index.html)に
とか挙げてるのなら、こういうときに意見の整理なり、科学的事実の把握なりした上で提言や、談話などの発表をするべきじゃないの?
政府から諮問されていないから答えなくていい、とかいう意見もあるけど、過去の提言とか別に諮問されてなさそうなのも沢山あるじゃん。こういう科学的なことで多くの人が混乱して困っているようなときに助けにならないって存在理由ないんじゃない?10億円って国家予算からしたら大したことないけど、年俸1000万円の人間の100人分の人件費だからね。Xみてたら若手研究者の給料は500万円くらいらしいから、若手なら200人分だよ。
政府に反対意見を言える組織は貴重だから、本来学術会議はあった方が良いし、政府は任用問題での干渉もやめるべきだと思う。しかし現状では反対でも賛成でもなんの意見も言えていないのだからタダ飯食らってるだけの無駄な存在と言われても仕方ないのではないか。
ミスが見つかった。ちょっとだけ修正しました。仕事に行くのでまた夜にでも修正するかも。
表題の文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが、これについては異なった見解が見られる
これはホーフェルドなどにみられる広義の権利と義務の対応に関する理解であって、一方の権利に対しては他方の義務が対応しているというものだ
二つ目はある主体が一般的な義務を果たさなければ一般的な権利を有しないというものである
これについては一つ目の立場から間違った理解であると批判されている
その理由としては人権は実定法ではなく生来の権利として有しているというものである
しかし同じ文言から異なる二つの解釈を導くことは可能であり、また前述の理由は正当な理由にならないのではないとも思う
例えば売買の買主は引渡請求ができる権利を有し、一方で売主は引渡を行う義務を負う
これは二者間に生ずる関係から導かれるものであり、主体は2つ必要である
そして上記のような関係を一般化することで権利義務関係について一般的な言明をしている
それによって国家と国民との関係についても権利と義務の対応が説明される
すると二つ目の見解は権利と義務の主体は同一であり、そのような主体における権利と義務の関係を述べていると言えるため、
両者の想定してる主体が異なっており、権利義務の内容も異なるのではないだろうか
確かに一つ目の見解からはある主体についての権利と義務は無数に考えらえることから二つ目の見解のような一般的な関係はないとの批判が考えらえる
しかしこと公法に関しては権利と義務の束については主体が同一とも考えられるのではないだろうか
例えばある人が特定の公法上の権利を国家に対して有する場合、主体は個人と国家であり二者間の関係となる
一方である人が国家に対して一般的な権利の束を有する場合には国家はある人を国民として権利を認めていることになる
このとき国家とは法人ではあるものの究極的には個人の結合体としての存在である
すると国家に対して権利を有する者は国家の一部として、自らを含めた国家の構成員に対して義務を有していることになる
ある個人は権利を有する主体であり、なおかつ国家の構成員としての義務を負う主体でもあるのである
この場合には同一の主体に権利と義務の対応関係が内在するのであり、一方のみでは成立しなくなる
上記の考えは人権については生来の権利であるとする自然法的な考えと異なり、憲法制定権者による内容画定であり、法的な理解として適切であると言える
この問題は何度も世に出てきていると思うが、法治国家のことを勘違いしている人がけっこういる。
表現の自由界隈からも「法律を超えたら表現の自由はない」ってのが無邪気に言われまくってるけどさ、じゃあ、「本日から漫画を描いてはいけない」って法律ができた瞬間、漫画を描く表現の自由はなくなるの?逆なんだよ。表現の自由が先にあって、それを侵さない範囲で規制が許されるだけ。
これに対して
自由を侵害する法律が作られたら法の手続きに基づいて侵害されないように法改正をするのが法治国家の自由の行使なのだ。
法治国家原理は、法律の法規創造力の原則(国民の権利を新たに制限し、義務を課す法規範は国民代表議会のみが作ることができ、行政が立法してはならない※)、法律の優位の原則(行政活動は議会制定法に反してはならない)、法律の留保の原則(国民の権利を新たに制限し、義務を課す行政活動は、法律によって授権されていなければならない)から成り立つ。これらのどこにも、自由を侵害する法律が作られたら、法改正を待つべきであり、あえて規制に逆らうべきではない、という議論は含まれない。
※これは行政に関する原理であるというのがミソで、私人同士で新たな義務を課すのは、原則として自由である。たとえば、100万円を借りるという金銭消費貸借契約を結べば、あなたはカネを返す義務を課されることになる。それに先だって国民代表議会の授権規範が必要であるというのは馬鹿げている。しかし、原則が自由だからこそ、社会における事実上の力関係によって一方的に立場が弱い契約を結ばされるということが起きる。そこで、契約の自由を制限する法律が制定されたり(例えば借地借家法を思い浮かべよ)、裁判所の判例法理によって調整が図られることがある。
二番目のツイートは、法治国家を(古代中国の法治国家の伝統もあって)遵法義務の問題と取り違えているだけで、些末な揚げ足取りではないかと思われるかもしれない。しかし、遵法義務の問題として考えてもおかしい。もちろん、国法は自らに従わない者に対して制裁の仕組みを用意することが多い。刑法にせよ、行政上の何らかの義務履行確保の手法にしても。刑罰という結果を避けるために従った方がベターであるというプラクティカルな議論としては意味があるだろう(事実としての強制秩序の問題)。しかし、それと服従義務とを混同するべきではない。たいていの法学者は、不正な法に対して服従する義務はないと考えているのではないか(例:ラートブルフ「法律による不法と法律を超える法」)。ラズなんかは、それを超えて、一般論としては国法への服従義務などない、と言っているようだ。
ただ、これは難しい問題で、誰が不正かどうかを判断するのかという問題がある。万人が自らに都合の悪い法を不正であると判断すれば、アナーキーとなり、宗教戦争の再来である※。しかし、実定法にただただ服従するべしと言えば、ナチスの法にも服従する義務があるのか(事実として強制されるからやむなく従うのではなく)と言われてしまう。結局、個々の法規範に則して個別的に判断する他あるまい。上記のツイートでいえば、一般論として漫画という出版様式の禁止を無視したからといってアナーキーに陥ると考えるのは馬鹿げているであろう。
現代の違憲審査制は、こういった正義と実定法のジレンマをなるべく起こさないようにするためにある。憲法に人権という形で示された一般的正義の原則に照らして裁判官が実定法を審査し、不正な法と認定した法規範の適用を拒否するという仕組みが我々の社会には導入されている。ただ、裁判官の目をすり抜けてどうしようもない実定法が作られることがないとは言えない。立法者と裁判官にさしあたって頼らずに正邪を判断する視点を持つことは、自由な民主的社会の市民であり続けるために必要なことである。・・・自分の頭で考えた結果、おかしな結論に到達する人もいるかもしれないのが頭の痛いところだが、それが自由であるということである。
悪法といえども国法に従う義務があり、悪法をただすには法改正に賭けるべきという態度は、肉屋を支持する豚と言われてもやむを得ない※。
※ひょっとすると熱烈なホッブズ主義者なのかもしれないが、ホッブズ主義者なら、本当に当該禁止によってアナーキーが避けられるのかをもうちょっと真面目に検討するのではないか。
参考文献
長谷部恭男『法とは何か[増補新版]』河出書房新社、2015年
おまけ:
それに反する法律は作れません。
こうした見解に対する批判は本文中にも書いた通りだが、この人の中では、薬事法(古い名前だ)の薬局距離制限規定が作られたことはなかったのだろう。薬事法は、自分に関連する分野ではないのか(薬剤師ではないから、違うかな・・・)。
以前どこかで耳にしたことがある。
法律学でも数学でもその楽しみは、1+1=2のような単なる技術的な操作だけに終わるのでなく、
「それを用いることは鉄板」「多数の問題に頻繁に出てくる」といったある種の、テクニックを超越した仕掛け、大技が隠されておりこれを一般にトリックという。
例えば数論の証明過程をみていて始終見るのが、フェルマーの小定理という有名な定理がいたるところに出てくることであり、それを使うのは鉄板といったものが多いことである。
法律でも、テクニカルにその理論を考察するだけでなく、その中には、裁判所による判例生成技術、三審制、などなど
法律適用技術を超えて多大な効果のあるトリックが多数埋め込めているのであり、法律理論の中にこのトリックを発見して確立し実定法学の中で使うことも一つの大技である。
| 時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 71 | 9373 | 132.0 | 39 |
| 01 | 75 | 10954 | 146.1 | 30 |
| 02 | 34 | 3658 | 107.6 | 49 |
| 03 | 22 | 2317 | 105.3 | 69.5 |
| 04 | 21 | 2569 | 122.3 | 82 |
| 05 | 31 | 2493 | 80.4 | 46 |
| 06 | 42 | 5237 | 124.7 | 40.5 |
| 07 | 81 | 5894 | 72.8 | 42 |
| 08 | 73 | 5822 | 79.8 | 36 |
| 09 | 157 | 10895 | 69.4 | 36 |
| 10 | 91 | 10932 | 120.1 | 43 |
| 11 | 117 | 12745 | 108.9 | 48 |
| 12 | 141 | 14871 | 105.5 | 34 |
| 13 | 119 | 12132 | 101.9 | 47 |
| 14 | 151 | 17411 | 115.3 | 61 |
| 15 | 123 | 11118 | 90.4 | 54 |
| 16 | 199 | 14738 | 74.1 | 39 |
| 17 | 408 | 36561 | 89.6 | 52 |
| 18 | 205 | 16281 | 79.4 | 39 |
| 19 | 179 | 12280 | 68.6 | 37 |
| 20 | 282 | 14507 | 51.4 | 12 |
| 21 | 197 | 16047 | 81.5 | 36 |
| 22 | 155 | 14499 | 93.5 | 25 |
| 23 | 532 | 132704 | 249.4 | 392 |
| 1日 | 3506 | 396038 | 113.0 | 45 |
ipadpro(113), ABCクッキングスタジオ(9), ボクシング漫画(4), 村上隆(115), ロボティクス(3), 釣っ(114), 中国拳法(4), タッチペン(3), 実定法(3), クロネコヤマト(5), 位置エネルギー(3), ドンファン(3), あてがえ(34), 今度(122), GW(27), タブレット(14), 弱者男性(102), 下方婚(34), 五輪(18), 教室(17), 疎遠(7), 高収入(13), 強者(33), JR(10), オリンピック(38), 弱者(63), 論理(30), ウマ娘(17), 開催(19), 中止(18)
(タイトル不明) /20210429172156(128), ■「あてがえ論」に見えるのは論理性が無いからなのでは? /20210429122335(29), ■賢いのに感染症対策が雑な人ってなんなの /20210429134530(19), ■やたらボクシング漫画・アニメが多い理由 /20210429005903(18), ■カンボジアのコロナ対策がすごい /20210429181923(13), ■そのうち「弱者職業」が流行ると思っている /20210429021213(13), ■昔のゲームがプレイできないのはおかしい /20210425125815(13), ■弱者男性は弱者男性同士でセックスすればいい /20210429130738(10), ■「大人の男女2人で会うと酒飲むかセックスしかすることない」 /20210429170206(10), ■ヤンキーやDQNも弱者男性に入れて貰えるんだろうか /20210429120751(10), ■男って肉体的に辛いこと何かないの? /20210429045438(9), ■マジキチな文章を書くとマジキチしか釣れない。 /20210429055259(8), ■anond:20210429122335 /20210429123309(8), ■弱者男性関連の話がしんどくなってきた /20210429213658(8), ■オリンピック開催 yes or no? /20210429232449(7), ■ケンタウロスって… /20210429094314(7), ■匿名ダイアリーで定期的にバズる /20210429125922(7), ■ABCクッキングスタジオの女性専用デーについて /20210429153748(7), ■ /20210429133521(6), ■男からのセックスの誘いって法律で禁止にすれば良くね? /20210429095727(6), ■「メーキャップ」って何のことかと思ったら"makeup"かよ /20210428211542(6), ■飯屋のくせに「酒が売れないから売上サッパリっすわー」とか言って恥ずかしくないの? /20210422220347(6), ■ /20200428225115(6)
ググってこういうのも見つけたぞ。
https://www.rengo-ilec.or.jp/seminar/doshisha/2008/12th.pdf
年表っぽくするとこんな感じか。
途上国において未整備の法律を立法する際に日本の法律を参考にする、みたいなことはあって(例えばこの間台湾著作権法の日本語訳を見て、それが日本著作権法の条文にそっくりだったことに驚いた)、その場合は当然向こうから立法担当者が留学しに来るし、こちらも一生懸命教える。
ぶっちゃけ話をすると,私はこれまで「別に査読はなくてもいいだろ」という話を延々としてきたのだが,ブコメやらtwitterやらで文系擁護派の一部の人が「人文系の学問は査読になじまないんだ!」みたいな議論を始めてることには正直困惑している.
日本語で文学関係の査読つき論文とかたくさん出てるし,というか英文で文学を専門にした査読誌は普通にあるし,国際的な和文査読誌も存在するし,問題のおおもとになった日本社会学会には和文と英文の査読誌があるわけで,文学や社会学の論文が本質的に査読に馴染まないなんてわけはない(実定法学は知らん).査読できるならした方がいいだろう.学術的ではないエッセイにまで査読を求めるのは間違っているけれど,新規性のある学術論文を査読制度に向いてないと言い募ることもおかしいと思う.
査読になじまない型の研究としては,たとえば史料校訂とかそういうのが挙げられるかもしれないけれど,それだってやろうと思えば外部チェックは入れられる.論集だってもし余裕があれば査読をした方が質が高まるし,選書系や新書系ではない単著も査読をした方がいいだろう(このへんは出版社の体力との相談になってくる面もあるので,今すぐに査読制度を取り入れろとは言えないことがもどかしい.twitterではOxford University Pressで査読つき単著を刊行した人が議論していたけれど,OUPと日本の出版社は体力違いすぎるんで……).
私が査読なしの論文を業績として認めるべきだと主張するのは,現在査読がなくとも良質な論文や著書が多く存在しており,それらを形式的に査読されていないという理由だけで無価値であるかのように扱うのは間違っていると考えるからだ.だが未来永劫査読すべきでないと主張するつもりはない.
もちろん査読という制度には様々な問題があるので,全面的な導入に慎重になるのはわからないでもない.文系分野での査読制度の拡大は止められない趨勢だろうが,一方で「査読されていないものの良質な文献」も産出され続け,全面的な査読制度の導入まではかなり遠いだろう.そのあいだにじっくりと議論をすればよいと思う.査読がないから文系は無価値だ! と絶叫するのでも,文系に査読はなじまない! と拳を振り上げるのでもなく.
id:hogefugapiyox 「査読がないから文系は無価値だ! と絶叫するのでも,文系に査読はなじまない! と拳を振り上げるのでもなく」ほんこれ/ 査読が実質なしという事で近年問題のpredatory journalについての考えも聞いてみたいかも
英語じゃないと業績として認められない分野のことはわからないけれど,和文論文が業績として通用する分野ではpredatory journalの話はあまり聞かない.
というのは,和文査読誌を出してる主体は,学会もしくは大学・研究所などの機関にほぼ限られるから.
学会が出している査読誌の多くは,投稿資格を会員に限定していて,多くの学会は年数千円の会費(院生や非常勤と常勤では価格に差をつけている学会が多い)を払いさえすれば誰でも会員になれる(推薦者が必要な場合もあるが,指導教官とか先輩とかに推薦してもらえばよほどのことがない限り会員になれる).つまり査読誌は会費で維持されており,こういう雑誌では投稿も掲載もふつう無料だ(流石に抜き刷りとかは金を取ることが多いだろうが).会員は会費を払い,見返りとして論文投稿の権利と雑誌を頒布される権利を得る(余談だが,日本の学術誌のOA化にあたっての障害の1つがこの「会費で学術誌を維持する」システムだった.会員は会費を払って雑誌を受け取っているのに,会費を払っていない者にまで無料で公開するなんて何ごとだ! というわけ.今でも,CiNiiやjstageで無料公開してるのは発行から○年過ぎた号だけです,みたいな運用をしている雑誌はある.
大学や研究所は言うまでもなく自分たちの研究費で雑誌を維持しているので,投稿料や掲載料を取らないことが多い.それって紀要じゃ,と言われるかもしれないが,投稿資格を学生や教員に限定していない場合があり,下手するとそのへんの学会誌よりも査読が厳しく良質な論文が載ったりするので,研究機関が出している=紀要というわけじゃない.これは外国でも割と見るんだよね.
もちろんごく稀に出版社が商業で出している学術誌もあるのだが,そういう奇特な出版社は文系の学問に理解があり非常に良心的なので投稿料を取らないことが多い.少なくとも私が知ってる雑誌はそうだ.
そして,日本語のアカデミアは豊かではあるが英語ほど広くないので,predatory journalが参入しようと思うほどの旨味がないし(全世界から微妙なデキの英語論文をかき集めてくるから商売になるわけでしょ?),たいてい自分のレベルでも投稿できる雑誌が探せばどこかにあり,場所を選ばなければ発表できてしまうわけで,わざわざ悪徳業者にカネを払うインセンティブがないんですわ.最近は学内紀要にも査読つきが増えてるから,紀要に出して「査読つき論文です(キリッ」というのも可能.ただ学会誌か紀要かは下手すると雑誌のタイトル見れば判別つくから,「あ,こいつ査読論文いっぱい書いてるとか言ってるけど全部紀要だわ」みたいなのはそれこそ業績リスト見るだけでわかったりする(まあ,学内紀要でもガチ査読していることはあるので,紀要だからといって低く見られるのも可哀想なのだが.うちの大学では学内紀要に落ちたという悲鳴もちらほら聞こえます).
なのでpredatory journalに関しては,うちらには関係ないね程度の感覚.id:min2fly氏の指摘は本当にそのとおりだと思う.
(……)査読は英語で“Peer review”,同じ分野の研究仲間(“Peer”)による評価を指すが,国際化が進み,大量の研究者・雑誌・論文が存在する状況において,果たしてある雑誌の投稿者,査読者,読者が一つの研究コミュニティの「仲間」となっているのか,ということになるだろう。互いに見知ったコミュニティであれば,でっちあげられた架空の研究者に査読を依頼するなどありえないし,不正に査読を通過して論文を掲載したところで,内容が稚拙であればむしろ評価を下げることになる。また,ある程度雑誌数が限られていれば,聞いたこともないハゲタカOA 誌に掲載された論文は不審に思うはずである。(……)査読はある程度限られた規模の研究コミュニティにおいて問題なく機能する仕組みであって,現状の国際化・巨大化した研究者集団の規模に適用するには限界があると言えるだろう。
以下、司法試験受けるどころかまともに法学で単位とれなかった法学徒崩れの一見解です。
まず、法学にもざっくり2つの分野が存在する。現実社会で運用されている実定法を研究する「実定法学」と、それ以外の法にまつわる研究をする「基礎法学」だ。
このうち、基礎法学には、少なくとも今「○○ 査読」でググった程度の範囲では、論文誌に査読がある。少なくとも法哲学・法制史・比較法学・法社会学あたりで査読付論文誌があるのは確実だ。勿論ないものもあるだろうし、そういうものに関しちゃガンガン批判していくのはありだろう。ただ、少なくとも「全ての法学分野で論文に査読がない」というのは明らかに間違い。
こちらはおそらく事実。というか、査読というシステムの意味があまりないということは考えられる。これは、実定法学というもののイメージがついていないと多分理解しにくい。
の三段階くらいレイヤーが存在する。ひとつ目は誰だろうと覚えてる当たり前の知識だけど、二つ目になると正解がないので絶対に個々人で異なってくるよね、3つめに至っては言うまでもない、みたいな話はおそらくある。
具体例を挙げよう。刑法には「刑罰は何のために存在するのか」という考えにざっくり2つの異なる立場が存在する。「ある個人が、悪とされる『行為』を行ったのでそれを罰しよう」という行為無価値論と、「社会的に悪い『結果』をもたらしたからそれを罰しよう」という結果無価値論だ。これは刑法における根本的な思想である。それらはどちらが絶対的に正しいとかではなく「どの分野でどの程度どちらの立場を優先するか」というレイヤーで争いがある。
具体的には、「心が壊れた人間による殺人」と「自分の赤ちゃんを殺そうとした人間を殺した母親」などだ。前者は刑法39条の規定により無罪となるとしよう。なぜなら、心神喪失状態での行為は「自分の行った行為に対する責任」を問うための刑罰を化しても無意味だからだ。その人は自分がおこなったことの意味を理解していないから、刑罰を科すことに意味がない。ふざけるな、という意見は多数あるだろう。心情的にそれは俺も理解できる。しかし、それでもなお刑罰を科すとするならば、それは「誰かが人を殺したという『結果』が悪いことである。だから、本人が自分の行為を理解していなくても、社会としてその結果をもたらした人間を罰しなければならない」という立場をとる、ということにならざるをえない。
では、「自分の赤ん坊を殺されようとしている母親が、殺そうとしていた人間を殺した」といった場合、その人間に対してどういう立場をとるべきなのか?「人を殺したという結果は社会にとって変わらないのだから、赤ん坊が殺された母親であっても刑罰を科すべき」という立場になり得るのか?
この話は、実のところ論理的には適切な例ではない。結果無価値論と行為無価値論は違法性阻却の議論で出てくるものであり、前者は心神喪失による有責性の阻却の話で、後者の緊急避難(追記:ブコメで「正当防衛ではないか」とありましたがそのとおりです。ありがとうございます……)による違法性阻却の話でしか出てこないからだ。もっと言えば刑法と民法と憲法では基礎になる論理が全く異なる。ここで俺が言いたいのは、実定法における「本当に基礎の基礎の大前提になる考え」は、法解釈において多くの矛盾を生み出す、ということだ。そこには「正解がない」。どの場面でどのような立場をとるか、それは1か0かで決められる問題ではなく、「ある場面ではAの立場を肯定し、別の場面ではBの立場を肯定する」、そういった解釈違いが、刑法民法刑法何百何千もの事例において発生する。それらに対して、「ある事例でAの立場をとり、別の事例ではBの立場をとる」という判断の組み合わせに、論理的な整合性をどのようにつけるか。それを生み出すのが、ざっくりと法学における「学説」と呼ばれるものになる。繰り返すがこれは刑法の例であり、民法や憲法では細かな部分は異なるだろう。だが、どの分野でも「学界の多数説」「学界の少数説」「実務における判例」の3つが異なる立場にある、というものが1つや2つくらいあるのは当たり前だ。それが実定法学の実情だ、と思っていいはずだ。
そんな現実において、あくまで俺の認識に限って言えば、その「矛盾しない解釈の論理体系を構築する」というのは研究をやる上では当たり前のことだ。論文出す以前に、研究ができるかどうかという前提の話。何の話をしているかというと、その能力を持っているかどうかを確認するのが「司法試験」であり、司法試験程度(そう、司法試験「程度」)を合格する能力がないと、法学研究なんてできない、というのが現実なのだ。全体的な解釈の整合性をとれているのは当然である。司法試験に合格すらできない人間は研究者になれない。「最低限の研究能力」という点で、院なりなんなりに進んでいる時点で最低限の自然淘汰が発生しているのは実定法学研究では当たり前の前提である。したがって「最低限の論理的整合性が取れてるかどうか」という意味での査読はそもそもない……というのが、院生の友人知人を持たない俺の、推測レベルでの解釈だ。そもそも論文を出せる環境にいる時点で、能力が保証されているからだ。
そして、そこからさらに「構築した論理体系による学説が『受け入れるに値するものか』」って話にまで踏み込むと、そのための「査読」ってなによという話がある。たとえば、心神喪失状態で何十人と殺した人間を無罪にすべきという、法学の論理的に整合性がとれている説を唱える人がでてきた場合、それを査読する意味とは何か。論理的には正しい解釈体系が、何十人もの法学者によって何十個と出来上がっているなかで、誰の立場をとるか。ここまでくると、正直なところ、査読がどうこうという話ではないのだ。はっきり言えば、「その学説を社会が受け入れるかどうか」って話なのだ。
この辺りを、法学を勉強したことがないひと、いや法学を勉強したひとですら勘違いしていることがあるけど、法と社会/法と政治というのは、ものすごく漸近している。法学の学説が受け入れ良レルかどうか、というのには少なからず社会的価値観/社会通念が影響しているし、法は決して固定的なものではなく、社会のなかで変動している。法は社会に内在しているし、社会に対して法は影響力を持つ。
そうした実定法学の特徴が生み出すのは、ある一定のレベルを越えると「学説が正しいかどうか」が「その学説が多くの人に受け入れられるかどうか」という問題に近づいていく、ということだ。法学部にいればよくあることだったが、どんなすごい教授でも、講義のうち何か1つくらいは、その人独自の(少数派)学説をとっていることはざらにある。だから、そういった場合に「査読があるかどうか」は問題にはならず、「発表した学説が受け入れられるか/無視されるか」という話が、業績や信用性、実力の評価として組み込まれるんじゃねえかな、とは思う。
まあ、それが客観的指標とは言いがたいのが問題だ、というのは絶対ある。だが、その場合はどのようなかたちであれば「客観的指標」による評価を法学が下せるのか、というのも問題になるだろう。
このように、「研究ができる/研究論文を出せる」という環境にいるというスクリーニングの上に、「それが社会的に受け入れられるか」が重要視されるという事後的なスクリーニング、その二つがあるからこそ、実定法学に査読の文化がない、というのはおおよそ雑な話としては、言えるのではないかと思っている。
で、これを読んで異論があるガチの法学研究者の人、補足というか訂正頼む。ぶっちゃけ法学でまともに単位とってない俺みたいなアホが補足いれないといけない状況にうんざりしてるんだ。真面目に誰か解説してくれ。
人権保障には2つの考え方があるとされる[5]。その第一は、いわゆる自然権思想に立つもので、個人には国家から与えられたのではない、およそ人として生得する権利があるのであり、憲法典における個人権の保障はそのような自然的権利を確認するものとの考え方である[5]。広辞苑では、実定法上の権利のように剥奪されたり制限されたりしない[1]、と記述されている。その第二は、自然的権利の確認という考え方を排し、個人の権利を憲法典が創設的に保障しているとの考え方である[5]。18世紀の自然権思想は19世紀に入ると後退し法実証主義的ないし功利主義的な思考態度が支配的となったとされ[2]、1814年のフランス憲法などがその例となっている[5]。
三浦瑠麗の件。
https://buzzap.jp/news/20180420-lullymiura-law-knowledge/
東京大学大学院法学政治学研究科 総合法政専攻博士課程を修了し、法学博士を取得しているものの、三浦瑠麗さんは農学部出身で自らの肩書きも「国際政治学者」。実は政治学が主分野で、法律についてさほど知識がないのかもしれません。
なんか「法学博士なのに法律の知識がないの?」って言ってる人がそこそこいて、Buzzap! までその認識なのは流石にどうなの、って思ったのでちょっと書いてみる。
まず、日本の大学の多くでは政治学は法学部で教えられている。早稲田大学や明治大学には政治経済学部があるが、東京大学、京都大学、慶應義塾大学、北海道大学、名古屋大学、など有名どころの大学はたいてい法学部の中に政治学科あるいはそれに準ずるものを持っている。
つまり、それらの大学で政治学を専攻した人は、法学について詳しい知識がなくても「法学部卒」になる。学位も「博士(法学)」とかになる。そういうところは学部の内側で法学専攻と政治学専攻に分かれていると思うので、法学部に入学したからといって法律の教育を受けているとは限らない。
なので、「法学」の学位を持っている人が全て法律の専門家とは限らない。ひょっとしたらアメリカ政治の研究者かもしれないし、ドイツ近代史の研究者かもしれない。あるいは政治哲学を講じているかもしれない。そういった人たちが日本の実定法について一般人よりは多少詳しいよね程度の知識しか持っていなかったとして、それはまったく不思議ではない。
学部・学位の名称と専門分野がリンケージしないというのは割と多い。たとえば歴史学・哲学・心理学なんかは多くの大学では文学部で教えられている(社会学なんかもここに入るかな)。結果として、「博士(文学)」(ただし文学のことはよく知らない歴史学者)なんてものが量産される。文学の知識がないのに「博士(文学)」を名乗っているのは別に彼らの責任ではなく、日本の大学と学位授与のシステムがそうなっているんだとしか言いようがないし、三浦瑠麗の「博士(法学)」も同じことだ。
もちろん、デタラメな法知識を知ったかぶってひけらかすのは恥ずかしいことだし、著名人がtwitterでそんなことをやったら炎上するのはしごく当然であり、その点で三浦瑠麗に擁護の余地はまったくない。存分に恥をかくべきだ。
だが、法学博士なのに法律について無知なのか、というような責め方あるいはあげつらい方をするのはおかしい。東大で政治学を専門に学んだ者の学位が「法学」になるのは彼女の責任ではなく単にそういうシステムだというだけの話であり、政治学について多少なりとも学術書を読んだことのある者なら経験的に知っている知識のはずである。そのような責め方は許容することができない。
あと農学部卒なことをあげつらうと小熊英二に返ってくるぞ。彼も学部は農学部出で修士から文系の院に入り、現在ではちゃんとその分野の学者として認知されている。学部まで理系として過ごしても、その後文転して良い業績を挙げているのなら何ら問題はないはずだ。もちろん学部教育というのは専門知のベースになるものであるから、「違う学部だったの? ああ、道理で……」みたいな事例が多々あることは否定しないが、三浦瑠麗憎しのあまり理系から文系に移ってきたという経歴を叩くなら反対する。似たような経歴を持つ別の学者のために。
なんというかもう、お前ら、流れ弾やめーや。
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務
員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、
債権者ら林野庁に所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法は全面的に適用さ
れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定
めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用
を排除されている。)
したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業の場所・従事
すべき業務等をはじめ、賃金・労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約を
締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条、
このことは、国家公務員法中債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労
使対等で決すべきこととし(労働基準法第二条第一項)、団体交渉による私的自治
に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも
のとみるべきである。
(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員の労働関係は実定法上か
らも、労働関係の実定法上からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命
令は行政処分の執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ
る。
債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁の
処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ
れない。
債権者ら林野庁職員の勤務関係は、実定法上公法関係として規制されているの
で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体
も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律
関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社が独立の企業体として制度
化され、その企業の公益的、社会的および独占的性格から、特に公社として私企業
との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう
けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設
けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無
視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係
には本質的な差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関
係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令を行政処分と規律している。以下
項を分けて詳述する。
二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもので
あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳
細に検討することなく、その勤務関係を直ちに私法関係であるとすることは、林野
庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。
周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係
は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と
しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ
うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁の行為が国の行
政機関として有する行政権の行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例
ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家
公務員法の規定のうち、一定範囲のものを適用除外しているが、一般職公務員であ
るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒、保障および服務の関係に
ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務
員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節
の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関
する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員の場合と同様に林野庁
職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院規
則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に
関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院
規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的行
為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業の役員等との兼業」に関する人事院
規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について
は、公労法第八条が一定の団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治
の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一
般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細
な規定が、右勤務関係の実体をどのようにとらえて法的規制をしているかが検討さ
れなければならないのである。しかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係
は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の
三、林野庁職員の勤務関係が公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ
るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな
る。
(三) そこでまず、学説を通覧するに、
(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁の建物を作つたり、官公庁が
器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場で商人と取引する。と
ころが官公庁が労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的な行為で
あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業だから事実上は強制
ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。
やはり官公庁の労働関係も労使関係は契約関係だという原則すなわち労働力の売買
取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ
り、
(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」
によれば、「郵政林野等の五現業の政府機関でも同様であつて、経済的な活動を行
うにとどまりその事業の性格が公共的なものとは認められないからその労働関係に
ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、
(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九
〇頁)によれば「公労法は争議権の制限をしているが、労組法・労調法と同じく労
使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ
右論稿部分は、公共企業体の従業員の労働関係が私法関係であることを強調する
諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ
ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体の従業員と同じ結論に達す
る筋合である。
また、地方公営企業労働関係法適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二
七日東京地方裁判所判決をめぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ
ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員の労働関係は私法関係と解すべきで
ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解で
ある(疎甲第一五号証)。
なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対
し地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法
第一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員の場合も全く同
じ現象がみられるのであつて、一般の国家公務員の場合は「免職」と規定している
(国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家公
務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国
(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理、
私的自治の原理に立つて立論している。
(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判
決(判例時報三六四号一四頁)
(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決
(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)
(3) 公立学校教諭の退職処分の無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案
とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決
(判例タイムズ九九号一〇〇頁)
(労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二日判決
(労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判
ことに、前記アンケートの対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日
判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの
が相当であり、本件解雇が行政処分であるとすることはできない。」と判示してい
るのであつて、地方公営企業体労慟関係法適用下の地方公務員と公労法適用下の国
家公務員とは、地方公務員法、国家公務員法の関係において、理論上および実定法
体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決の論理は、そのまゝ本件
(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ
ていた無定量の勤務の観念は否定され、公務員の勤務関係は契約関係とみるのが適
当とされるようになつた。
そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員は特別職
とされていた。
ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される
に至り、一方国鉄、専売事業は公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ
ることとなつた。
その後昭和二七年八月一日公共企業体等労働関係法として改正施行され、いわゆ
る五現業もまた、この法律の適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結
権を取得した。
右法改正(労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府は
「公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格、実態
が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま
すので云々」と説明しているのである。
昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法の規定の適用除外
を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年
法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし
第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条、一般職の職員の
給与に関する法律、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二五年法律一八〇号)
の規定は除外されるに至つている。
(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場に
立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。
その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条の解雇の問題である。
公労法第一八条の解雇は同法第一七条違反を理由として労働契約を解除するいわ
ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし
て五現業庁は公労法第一七条違反に国家公務員法における懲戒処分をもつて対処し
ようとする。
従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条と国家公務員法第八二条が選
択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI
LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と
「使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判を
受けざるを得ない。
(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係を規律する実定
(イ) 公労法第八条の労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の
原則に立つている。
(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会に対応する公共
企業体等労働委員会が設置され、人事院に提訴することができない。
(ハ) 右公共企業体等労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服
申立が許されない。(公労法第二五条の七)
(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労
働組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな
いことである。(公労法第四〇条第四項)
右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す
る処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること
(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人部事務局長であつ
た福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当区事務所に配置換
(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当区事務所に配置換
(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署経営課経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換
(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人部書記長であつた白
河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当区事務所に配置換
職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債
務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情と希望を確かめる取決
めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者は債権者らに事情を聴くこと
(3) 配置換が組合の学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者
自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例
営林署長会議において、「組合の学習運動は地本の指導下に最近活発になつてい
る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状
態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること
(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四
月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。
(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会は昭和四二年五月に開催
され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者は組合青年婦
人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織の破壊を企図している時点におい
て、右大会は特に重要な意義を有するのであるが債権者らは右大会の準備、運営に
不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され
(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし
ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ
けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて
しては家庭生活を整理する余裕がない。
しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者は組合
に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人部大会において新役員が改選される
まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に
おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言
明するに至つた。
そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残
(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身
廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくまで懲戒処分を避けるため
の暫定的なもので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する
程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在
帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活を破壊し、組合活動の自由を放棄するか二
者択一を迫られている。
以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活
の破壊、組合活動の自由の剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。
(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ
ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係は公法関係でなく、私法関係であ
つて本件は民事訴訟法上の仮処分の対象となる法律関係である。すなわち、 債権
者ら林野庁職員については、公共企業体等労働関係法(以下公労法という。)が適
用され(同法第二・三条)、国家公務員法の規定の一部は適用されない。(公労法
第四〇条)
公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権・労働協約締結権があり(公労法
第八条)労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法第
一六条)ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意
の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限
によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実
態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一
のものであり、債権者らが所属する労働組合と林野庁には公労法第八条第四号に関
する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否
しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部と対応
営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚
書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する
メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に
関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。
したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係で
はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである。
(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず
しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその
区別のメルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体
そこで人の使用されている関係が私法関係であるか公法関係であるかは、使用者
が私人であるか国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも
のではなく、その関係が慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて
もつとも歴史的には国家が本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合、
その任に当る個人の人権を犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの
理由から、上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法や実定法が生れて来たけれ
ども、国家が本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業
員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもので
はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号
八六頁参照)